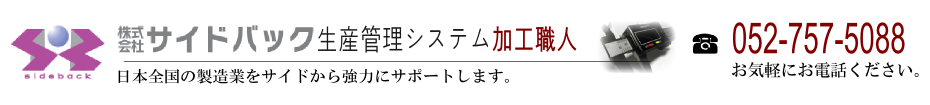在庫管理につきまして
在庫管理につきまして
今日はうるう年の月末で、あまり好きでない月末の事務作業が終わりました。
金属で残材が発生する事でサイズが変わったり、ミルシート管理が必要な在庫管理について、加工職人シリーズの説明になってしまいますが書いてみます。
納品した製品のミルシート番号を客先に対し提示しなければならない材料を取り扱っている場合、在庫もミルシート番号がわかる単位で管理する必要があります。実際はチャージ番号が入荷時に送られて来ますので、その番号を在庫のキイの一つで登録します。
残材管理を行う場合は、定尺材だけでなく、残材サイズの在庫も発生しますので、在庫サイズは可変長のサイズになります。
棒材であれば長さが変わるだけですから、管理は単純ですが、板材の場合どこまでの在庫管理が必要なのかによって管理方法は変わります。
高価な材料加工の場合は、残材も大切な資産です。またスクラップさえ資産の一部です。
メタルマイスターはステンレスの板をレーザー、シャーリング等で切断して、曲げたり、溶接して組み立てたりして製品を製造する業務運用を支援するシステムです。
レーザーで切断を行う場合、如何に効率よく切断するかによって歩留まり率が向上します。
これを完全にシステムで行う場合はCADでネスティングを行い、在庫形状もイメージまで持たせてCADシステムと連携させる事で実現できます。
しかし、ネスティングは出来たとして、残材の在庫管理をイメージまで持たせて、CADと連携という事になりますと、かなり高額なシステムになってしまうという事で、メタルマイスターではCADとの連携はまだ行っておりません。
替わりに、板取切断処理という指示画面があり、そこで当日切断予定の同じ材質、板厚の作番を抽出表示して、母材は人間が選択して、板取切断指示書を作成します。
切断現場では板取切断指示書で切断を行います。この指示書には、その母材で切断する作番の明細が印字されているので、その通りに切断して、実績登録も、個別に行わなくても、母材単位に1回の処理で実績登録が出来ます。
残材は切断後にサイズを測ってハンディターミナルで計上します。残材ですから単純なサイズではありませんので、メインサイズとサブサイズを別にもたせ、ある程度在庫問合せで判断が出来るようになっています。

在庫から出庫時は指示した母材(現品単位)以外の母材でも同じ材料であれば変更できますが、切断時の変更は出来なくしています。
また歩留まり管理では、投入母材に対し、完成製品重量、残材重量でスクラップ量を計算して、それに対し、計測事績スクラップ重量で差を求め、その差を原価計算で材料原価に按分できるようになっております。
棒材の場合、全てではありませんが、受注登録後、材料出庫指示画面が開き、自動で製品の長さで引当を行い、現場では基本的に指示した材料を使う。どうしても使えない場合だけ、先の出庫指示画面で母材の変更を行います。この運用でで在庫はかなり正確に管理されています。しかしこれは会社としての強い命令系統がありませんと、現場から協力を歩得る事は出来ません。
ハンディターミナルを活用した棚卸
1.棚卸準備処理でコンピュータ在庫を確定します。
2.棚卸の場所別に置き場カードを作っておき、置き場ごとにカードを添付します。
3.棚卸開始
①置き場をスキャンさせます
②その置き場に置かれている在庫の現品票のバーコードをスキャンします。置き場での読み込みが終了したら、登録ボタンでサーバに結果を送ります。
③サーバ側は各所から送られてくる棚卸データを置き場単位に集計して、調査が必要な場合は、置き場に戻って調査を行います。
現品個々の棚卸しの為、手作業時は大変でしたが、現在は半日で終了して、大変喜んでいただいています。
ブログランキングに参加しています。 気に入った記事や参考になったと思った時は応援のポチを頂けると嬉しいです。
a:6447 t:2 y:3