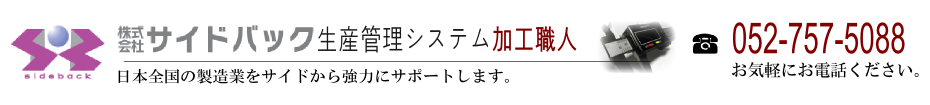コンピューターの歴史とレベルアップについて
コンピューターの歴史とレベルアップについて

私が関わったコンピューターは大型汎用機、オフィスコンピューター、PCネットワークシステムです。
オフィスコンピューターまではハードウェアメーカーが主体で、メーカー毎にOSも分かれていました。
私の場合、最初はガス溶断機メーカーの社員として、富士通の汎用機を使ってバッチシステムを構築して、生産管理、資材管理、原価管理を行っていました。
言語はCOBOLでコーディングシートにコーディングして、それをキーパンチャーにお願いして紙テープに作成してもらいます。
そして、それを本社工場(埼玉)に送って、それを本社工場の電算室の方が、コンパイルしてリストとコンパイル結果を送り返してもらうという、ものすごく非効率的な製造を行っていました。
当時は、まだ複数端末が同時に動作するマルチワークとか、他拠点とオンラインで繋いで処理を行う事は、まだ先の事でした。マルチワークの事を多重処理といっていました。
月末になると、本社工場まで月末締切りに行き、徹夜でデータを取り込んで、エラーがあれば、紙テープで修正データを作成して、結構大変な作業でした。
でも懐かしく良き時代でした。いくら徹夜をしても、全額残業代が請求できましたので、常に同期の倍は頂いていました。
汎用機自体は現在も基幹システム用コンピューターとして使われていますが、現在のPCシステムの前に、オフコンの時代がありました。
最初は1台だけのフロッピーディスクで動作するデータライターのように小型のコンピューターでびっくりしました。言語は簡易言語からCOBOLへと進化してゆきました。


オフコンは、フロッピーからDISKベースになって、マルチワークになって、日本語になって、カラーに切り替わるだけで、ものすごく大きなインパクトがあって、大きなレベルアップ推進力でした。
しかしオフコンはメーカー毎の高い壁があって、メーカーを変えることは、今までに構築したソフトウェア資産を全て使わず、新たに構築しなければならず、その為か、我々提供者サイドは、少々殿様商売でした。
お客様の要望に対し、だから出来ませんという、否定的な立場でシステムを構築してきました。BuffaloのM社長に、うちに来ているSEは道路工事の旗振り以下だと言われたことがあります。(できる事しか出来ない)
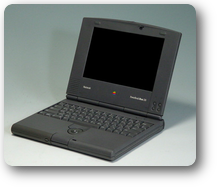
そんな頃、PCシステムが登場してきました。最初はMACのノートPCのデモを見て、あまりのオフコンとの違いに愕然としました。
この頃から、インターネットとかメールが使われてきました。
しかしPCがオフコンに切り替わるには少し時間が必要でした。
当時のPCのプログラマーは個人的趣味の、オタクっぽい若い方が多く、オフコンのSEと会話が成り立たないくらい違う人種でした。
当初出来上がったシステムは一見格好良いのですが、実際事務作業では使えない代物でした。
そんな何やかんやをしながら、オフコンのSE、プログラマーがPCの勉強をして、どうにかオフコン並みの操作性のあるPCシステムになってきました。
そうなりますとPCの方は他の各種機能がありますので、オフコンとは比べないくらい、全体にレベルが向上しました。
何といってもOSが同じという事が、システム提供側も、お客様側もあり難いことです。
現在はスマートフォンのSE、プログラマーが不足しています。
以上のようにコンピュータ自体の記憶容量が増え、処理速度が速くなり、小型化し、環境が変化(ネットワーク等)のスピードは速く、魅力的です。
しかし残念ながら、業務管理のソフトウェアの考え方は、私が大昔汎用コンピューターで紙テープでシステムを作っていた頃と、殆ど変わっていません。
標準的な財務、販売管理などはパッケージ商品化されていますが、製造業のシステムは全体的に見て一番遅れているのではないでしょうか。
これはシステムを提供する側に大きな責任があります。生産管理だから、原価計算だからパッケージ化は難しいとかで、業務を理解しているSE要員の教育が出来ていません。
生産形態別に汎用的なパッケージシステム化して、カスタマイズは殆ど行わなくても稼動が出来るような、安価なシステムを作り
それをインターネット上のウェブサイトで販売して、買う側もベンダー任せから、自社に合うシステムをネット上で検索して探して、一寸だけ勉強していただいて
提供者である、我々と交渉して導入できれば、一番効率的です。
近い将来、きっと物品販売のようにシステム商品もそうなってゆくと信じて、その為の商品整備と、販売の仕組み作りを、してゆきます。
ブログランキングに参加しています。 気に入った記事や参考になったと思った時は応援のポチを頂けると嬉しいです。
a:4645 t:1 y:2